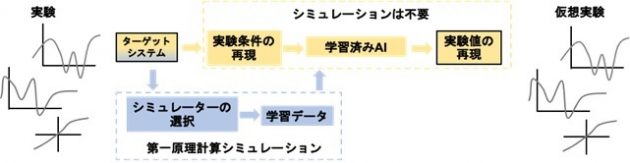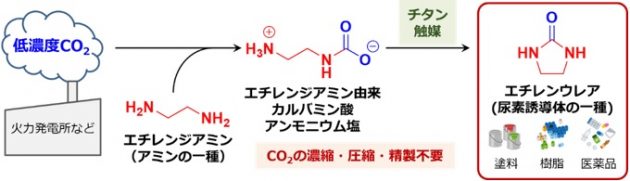産業技術総合研究所(産総研)と豊実精工(岐阜県加茂郡)はこのほど、常温衝撃固化現象を活用したエアロゾルデポジション(AD)法を最適化し、3次元的表面に防錆性と耐摩耗性を付与できる低環境負荷の常温セラミックコーティング技術を共同開発した。
機械部品の防錆加工に汎用される硬質クロムめっきは、硬度と処理コストに優れるが、特定有害物質の六価クロムを使用し、欧州のRoHS指令など多くの規制を受けるため、機械的耐久性や防錆性に優れた六価クロムフリーの表面処理技術が求められている。代替技術の三価クロムめっきや溶射法は、密着性や耐摩耗性、膜厚制御性などが劣っている。
今回AD法を活用し、平面と3次元形状の鉄系部品表面への高い防錆性・耐摩耗性の量産レベルのセラミックコーティング「ERIN処理」技術を開発。ドライコーティング非溶液プロセスで、溶射法のようにセラミック微粒子を溶かさないため、凝固収縮に伴うクラックやポアが発生せず、高い硬度と密着力をもつセラミック膜を形成し、高い防錆性や耐摩耗性が期待できる。
基材に吹き付けられたセラミック微粒子は、衝撃でナノサイズの微細結晶片に破砕し、流動、再結合して強固な密着力と機械強度をもち、厚みのある緻密なセラミック膜を形成。成膜速度は速く常温処理であるため、熱に弱いプラスチックなど様々な基材へも適用できる。ピンホールやクラックの抑制にはセラミック粒子が均質なナノスケールの微細結晶片に破砕されることが重要で、基材の表面粗さ(凹凸形状)、セラミックコーティングの膜厚、基材の硬度、吹き付け角度の設定により、複雑な3次元構造体表面にも剥離のない均質な被膜を形成することを実証した。
今後、豊実精工は防錆性や耐摩耗性が要求される小型精密機構部品などの年内の製造販売を目指すとともに、六価クロムフリーの機能めっき代替技術としての事業展開を図る。
産総研は、原料粉末の合成や高度化などで同技術の量産性を向上し、低コスト化や大型構造物への適用拡大を検討するとともに、欠陥のない緻密3次元セラミックコーティング技術として、電子部品やエネルギー関連部材用途への応用展開を進めていく。