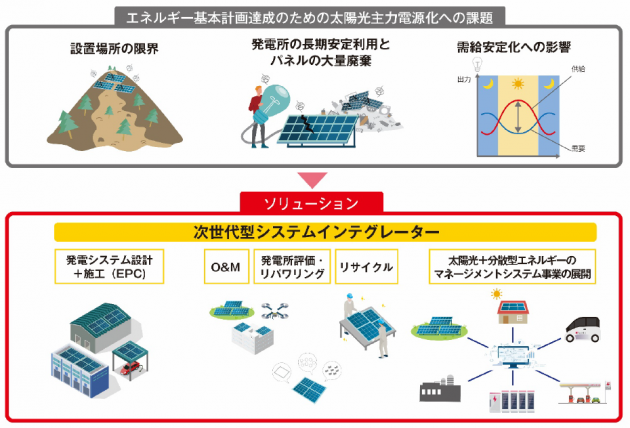新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、経済産業省が「TCFDサミット2021」で公表した、「ゼロエミ・チャレンジ企業」(第2弾)の約600社の企業リストに、政府の「革新的環境イノベーション戦略」に基づきNEDOが実施中の45のプロジェクト(PJ)に参加する企業488社と11の技術研究組合が含まれている、と発表した。
同省は「ゼロエミ・チャレンジ企業」を、脱炭素社会の実現に向けたイノベーションに果敢に挑戦する企業と位置づけている。昨年の第1弾では約300社のリストを作成し「TCFDサミット」で公表していた。
今回は、新たに農林水産省と企業の選定について連携をするとともに、NEDOでも17のプロジェクトが追加対象とされたことで、約300社がリストに加わり、掲載企業数は合計で約600社と大幅に増加。その中に、NEDOのPJに参加している499の企業・団体が含まれる結果となった。
NEDOは引き続きゼロエミ・チャレンジに協力し、脱炭素社会の実現に向けたイノベーションの加速に貢献する。