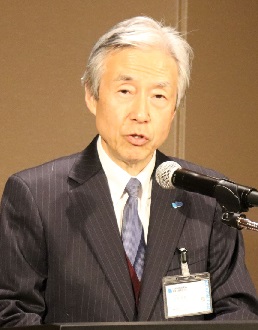新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と大崎クールジェンはこのほど、CO2分離・回収型酸素吹石炭ガス化複合発電(CO2分離・回収型酸素吹IGCC)の実証試験を開始した。
実施期間は2019年12月25日から2021年2月28日までを予定し、中国電力大崎発電所構内に建設した実証試験設備で行う。両者は石炭ガス化燃料電池複合発電(IGFC)とCO2分離・回収技術を組み合わせた革新的な低炭素石炭火力発電の実証事業に取り組んでおり、今回の実証試験はその第2段階となる。
なお、大崎クールジェンは中国電力と電源開発の共同出資会社。同実証試験では商用発電プラント(1500℃級IGCC)を想定して、IGCCでガス化したガス全量に対してCO2を90%分離・回収しながら、現状で最新鋭微粉炭火力発電方式と同等となる、送電端効率(高位発熱量基準)40%の達成見通しを立てることを目標としている。
酸素吹IGCC実証試験設備にCO2分離・回収設備を付設して、CO2分離・回収型酸素吹IGCCシステムとしての基本性能やプラント運用性・信頼性、経済性などを検証する。この実証事業では、酸素吹IGCC実証(第1段階)、CO2分離・回収型酸素吹IGCC実証(第2段階)、CO2分離・回収型IGFC実証(第3段階)の順に実施する。
2017年3月から開始した第1段階の実証試験では、170MW規模の実証プラントとしては、世界最高レベルの効率となる送電端効率40・8%(高位発熱量基準)を達成し、実用化後の商用発電プラントに換算して、送電端効率約46%(高位発熱量基準)の達成に見通しが立った。今回、第2段階となるCO2分離・回収型酸素吹IGCCの施設が完成したことから、試運転を経て実証試験を開始した。
同実証試験の目標を達成することにより、同事業とは別に開発が進められているCO2の利用・貯留技術と組み合わせることで、CO2をほとんど排出しない、ゼロエミッション石炭火力発電が実現できる。今後、CO2分離・回収型酸素吹IGCCシステムを確立し、国内外で同技術を普及させることで、世界全体のCO2排出量抑制(地球温暖化対策)への貢献を目指す。