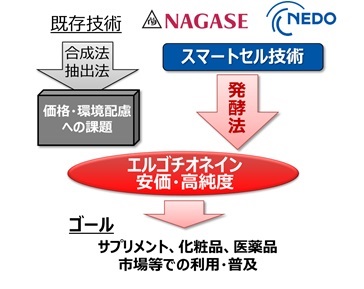新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)はこのほど、バイオジェット燃料の普及に向けた市場形成や社会実装のためのサプライチェーン構築とカーボンリサイクルのための原料基盤技術を強化する研究開発に着手すると発表した。事業化スキームや経済性を検証し、バイオジェット燃料の市場形成に向けたサプライチェーン構築を促進する。
航空業界にとってCO2排出量削減による地球温暖化抑止対策は喫緊の課題だ。バイオマス由来のバイオジェット燃料導入は実現可能性が高く、海外では廃食用油由来のバイオジェット燃料が実用・商用化され、国内でも今年中のバイオジェット燃料の国内定期便デモフライトを予定するなど、事業化の動きが加速している。
こうした中、NEDOは2017年度から「バイオジェット燃料生産技術開発事業/一貫製造プロセスに関するパイロットスケール試験」を実施しており、2030年ごろの商用化を目標に一貫製造技術の確立を目指した研究開発に着手する。
実証を通じたサプライチェーンモデルの構築では、製造技術ごとに「油脂原料からの水素化・脱酸素化処理」(ユーグレナ)と「短繊維パルプ由来エタノールの脱水重合」(Biomaterial in Tokyo、三友プラントサービス)の一貫製造技術の確立と、原料調達・製品供給などの事業スキームや経済性を検証する。
微細藻類基盤技術開発では、特長の異なる大量培養方法「海洋ケイ藻のオープン/クローズ型ハイブリッド培養」(電源開発)、「熱帯気候・屋外環境下での発電所排気ガスを利用した大規模微細藻類培養」(ちとせ研究所)、「微細藻バイオマスのカスケード利用」(ユーグレナ、デンソー、伊藤忠商事、三菱ケミカル)の実証と生産コスト低減や副生物の有効利用にも取り組む。また微細藻類研究拠点の整備と商用化の課題解決・標準化を図る「微細藻類研究拠点および基盤技術の整備・開発」(日本微細藻類技術協会)も採択した。事業期間は2024年度までで、今年度予算は49.5億円。
同事業を通じてバイオジェット燃料の普及に道筋をつけ、航空分野での温室効果ガスの排出量削減に貢献するとしている。