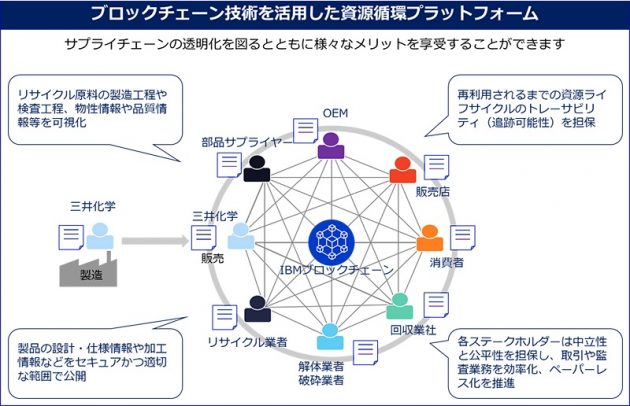三菱マテリアルはこのほど、工場から排出されるCO2のCCU(二酸化炭素回収・利用)技術の実証試験を同社九州工場黒崎地区(北九州市八幡西区)で開始すると発表した。
セメント焼成用キルンなどの高温加熱炉を使う製造プロセスから排出されるCO2を分離・回収し、水素と化学反応させてメタンなどを合成する技術の開発を進めており、7月より実証試験を開始する。今後は得られたメタンなどをセメント製造の熱エネルギーとして再利用するための技術開発にも取り組み、将来的にはメタン以外の有価物への変換を含めた幅広い用途展開に向けた技術開発を進めていく。
同社は「脱炭素社会の構築に貢献」を掲げ、グループ全体の温室効果ガス(GHG)排出量を2030年度までに17%削減(2013年度比)、2050年までにカーボンニュートラルを目指す中長期目標を設定。それに向け、従来の省エネ対策や電化では削減が難しい、セメント焼成用キルンなどから排出されるCO2を回収・利用することで、カーボンニュートラルな熱エネルギーにより石炭などの使用量削減を図り、セメント工場からのCO2排出量の抑制を目指す。
今回の技術開発を通じて得られた成果を同社グループに展開し、CO2排出量の削減を進めることで、脱炭素社会の構築に貢献していく考えだ。