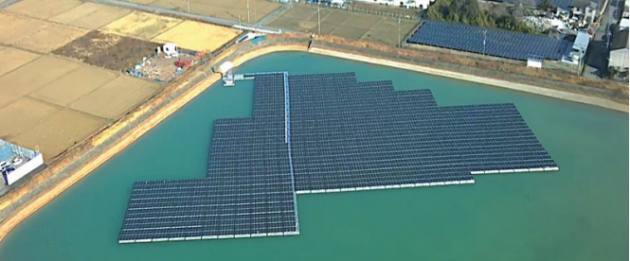東レ、東京電力ホールディングス、山梨県の3者はこのほど、甲府市米倉山(こめくらやま)の電力貯蔵技術研究サイトで技術開発を進めてきたP2G(パワー to ガス)システムの成果を発展させ、さらにカーボンニュートラル(CN)の実現を目指した新たな事業への挑戦に向け、共同事業体の設立を検討していくことについて合意した。
2016年度から、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託事業として、3者が共同で技術開発を行ってきたP2Gシステムは、大型の水電解装置や水素出荷設備などの施設全体がおおむね完成。今年6月から、山梨県内の工場やスーパーマーケットで水素を利用する実証試験を全国に先駆けて開始する。
こうした中、P2Gシステムの技術をさらに発展させ、山梨県内外での水素供給事業を可能にするとともに、国が創出する新たな基金事業へも積極的に取り組んでいくため、今回の合意に基づき、共同事業体「やまなし・ハイドロジェン・カンパニー(YHC)」(仮称)の設立に向けた検討を進める。
山梨県は、2050年までに温暖化ガスを実質ゼロにする脱炭素社会の実現に向け、P2Gシステムの実用化を加速し県内外への普及を図る。そして、さらなる高効率化・大容量化に向けた技術開発を進め、エネルギー需要家の化石燃料の利用をグリーン水素に大きく転換させ、新たな水素エネルギー産業の創出を目指す。
東京電力HDは、非化石エネルギーの推進を通じて持続可能な社会の実現に貢献するとともに、産業部門の電化や水素の技術開発により、脱炭素社会の実現に貢献していく。
東レは、「サステナビリティ・ビジョン」の中で、2050年に温室効果ガスの排出と吸収のバランスのとれた世界などを目指すことを掲げ、地球環境問題や資源・エネルギー問題の解決を通じて社会に貢献することを目指している。電解質膜、電極基材などの水電解・水素圧縮や燃料電池向け材料の開発、製造および販売を通じて、CNを可能とする水素製造(水電解)や水素インフラ(圧縮・貯蔵)、水素利用(燃料電池)技術の発展に貢献していく。