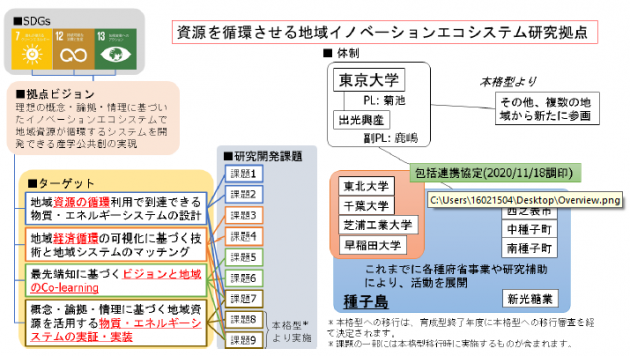花王はこのほど、奈良先端科学技術大学院大学と共同で材料工学分野にディープラーニング技術を適用する手法を開発し、「第43回ケモインフォマティックス討論会(オンライン開催)」で発表した。今まで長期間を要した素材開発の高速化に寄与し、さらにAIの予測の解釈を明らかにすることで新しい素材開発の手掛かりとなることも期待される。
商品開発には優れた素材の開発が必要だが、今まではトライアンドエラーの繰り返しで、莫大な時間と費用が掛かっていた。ディープラーニングによるAI予測では、大量の化学反応プロセスデータの取得に多くの費用が掛かり、実用化には至っていない。今回、触媒と樹脂を例に、少量データで活性やガラス転移点の予測ができるディープラーニング技術を開発し、予測に至る解釈の方法も確立した。
まず、界面活性剤製造などに用いる2級アミンとアルコールの反応で、反応時の銅触媒の微細構造を電子顕微鏡で撮影。一部切り出し・複写などの処理で143枚の写真を1万枚に増やし、その活性度の違いを学習させて活性予測モデルを作成した。作成した予測モデルは非常に高精度であった。活性箇所の画像を作成したところ、触媒のマクロポア(50㎚以上)周辺の構造が活性に影響していることが予想された。高活性触媒の開発が期待される。
次にポリエステル樹脂の化学構造からガラス転移点を予測するモデルを作成した。不足するデータ量は一般公開される外部の化学構造データベースで補い、予測モデルを作成した。さらに、ガラス転移点に影響を与える官能基を画像化した。予測モデルはガラス転移点を精度よく予測し、またベンゼン環に対する官能基の置換位置(オルト位、メタ位、パラ位)がガラス転移点に大きく影響することが分かった。この知見を生かして、ガラス転移点をコントロールできると考えられる。
ディープラーニング技術で少量のデータからでも予測モデルを作成する技術を開発し、画像により予測を解釈する方法も確立した。ほかの様々な素材開発にも応用が可能で、今後はデータ科学と研究者の知見を融合させて効率的な素材開発が可能になることが期待される。