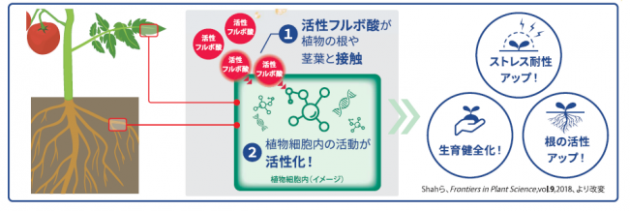ランクセスはこのほど、高温多湿条件下での高い耐加水分解性とレーザー透過溶着に適した良好なレーザー透過性を兼ね備えた新しいポリブチレンテレフタレート(PBT)コンパウンドを発表した。
PBTでは困難とされた耐加水分解性とレーザー透過性を両立。さらに反りが少なく寸法安定性が高いため、コンパクトで複雑な形状のハウジングに適し、スワール制御用メカトロニックアクチュエータのハウジングに使用できる。
小型・複雑形状のコンポーネントの生産法に、レーザー透過溶着法がある。レーザー光エネルギーを利用した熱可塑性プラスチックの接合方法の1つで、レーザー透過性のコンポーネントを通過したレーザービームが、その下にある2層目のコンポーネントに吸収され発熱し、コンポーネント表面を溶融。その熱で一層目のコンポーネントの表面が軟化し、2層のコンポーネントの間に強力な溶着シームを形成する。
ハウジングのレーザー透過部分には黒に着色されたレーザー透過性の「ポカンB3233HRLT」、レーザー吸収側には「ポカンB3233HR」が使われる。「ポカンB3233HRLT」は黒く着色されても溶着に用いられる光波長域の透過性が高く、部品は安定・効率的に溶着される。また高温多湿環境下での耐久性は米国自動車技術者協会(SAE)のプラスチック耐加水分解性の長期試験で実証され、125℃まで耐え、車のボンネット内の高温・高湿度環境にも耐えられる。
なお、スワール制御アクチュエータとはディーゼルエンジンなどのエアマネジメントシステムの一部で、吸気を制御すると同時に十分な乱気流を確保する役割を担う。燃焼プロセスを最適化しエンジン効率を高める上で重要な役割を果たし、最終的には燃料消費量の低減につながる。