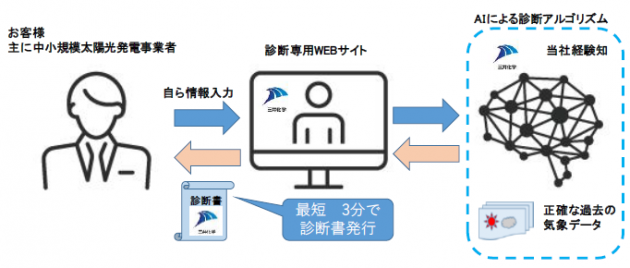竹中工務店と国立極地研究所はこのほど、2022年度から南極内陸部のドームふじ近傍に、屋根の骨組み(架構)に炭素繊維強化プラスチック(CFRP)を活用する氷床掘削施設を設置し効果の検証を開始すると発表した。現在策定中の南極地域観測第Ⅹ期6カ年計画(2022~2027年度)において、南極内陸部(沿岸から約1000Km)のドームふじ近傍での氷床コア(アイスコア)掘削が予定されている。
掘削施設の建設に必要な部材は、南極観測船「しらせ」で日本から南極大陸沿岸の昭和基地へ輸送し、その後、昭和基地からドームふじへ雪上車で数週間かけて運搬する必要がある。また、現地での組み立ては、限られた人数の観測隊員により進められる。これらのことから、建物の強度を維持しつつも、輸送や組み立ての効率化のために部材の軽量化を図ることが重要な課題となる。
さらに、現地は年平均気温がマイナス50℃を下回る厳しい気象環境にあり、部材に使用される素材は低温に強いことが必須条件。こうした課題の解決を図るため、両者は、CFRPの①軽量、②高強度、③伸び・縮み・変形しにくい、④錆びない、などの特長を生かし、輸送にかかるエネルギーの削減、現地での組み立ての簡易さ、現地の過酷な気象環境への対応といった観点から、南極の内陸施設におけるCFRPの活用に向けた共同研究を、2019年から推進してきた。
今回の実証試験では、南極のドームふじ近傍に設置する掘削施設の屋根架構にCFRP素材の部材を適用し、部材軽量化による効果を検証するもので、今年12月に昭和基地まで輸送した後、2022年度にドームふじ近傍の掘削地点に設置、その後、2028年まで現地で経過観察を行う予定だ。
CFRPは、一般炭素鋼(鉄)と比べて重量が5分の1と軽量でありながらも5倍の引張強度をもつ。試作の結果、屋根架構にCFRPを用いた場合には、従来の鉄骨屋根と比較し約40%の重量削減を見込めることが判明した。これにより、現地で組み立てを行う観測隊員の負担を軽減するとともに、部材の輸送・組み立てにかかるエネルギーを大幅に削減することが期待され、これらの効果は脱炭素社会の実現にも寄与すると考えられる。
国立極地研究所は今後、南極に設置するほかの観測施設へのCFRPの活用を検討する。一方、竹中工務店は、CFRPの建設利用に関してさらなる検討を進めるとともに、一般建築に向けた適用も推進していく。