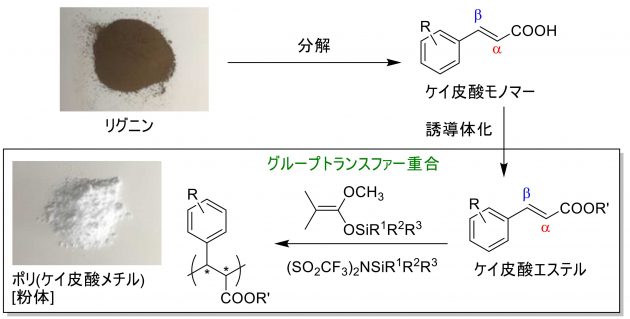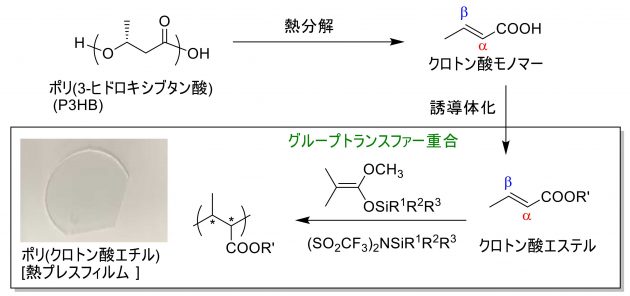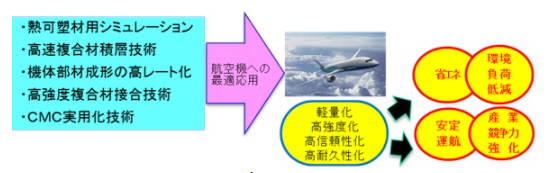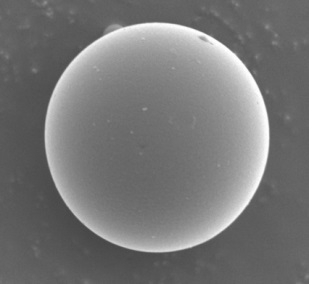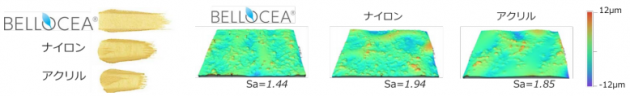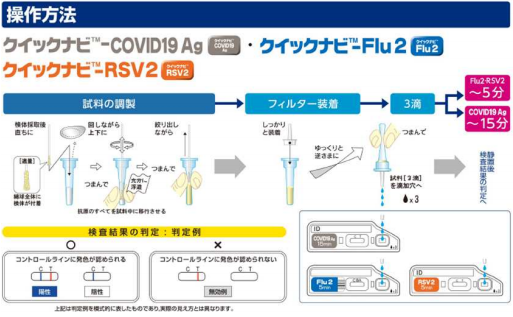積水化学工業の住宅カンパニーはこのほど、国が推進するコミュニティZEHの考えを取り入れ、レジリエンスを強化した分譲地「スマートハイムシティ&プレイス」を全国で順次展開すると発表した。
住宅カンパニーでは、環境・社会課題解決による「顧客価値」と、利益ある成長による「事業価値」の両立で、ESG経営を推進。スマートハイムシティにコミュニティZEHを展開することでCO2排出量削減などにより環境負荷軽減に寄与するだけではなく、防災拠点となる分譲地を全国へ広く展開し、地域社会へ貢献する。
国は災害の激甚化・頻発化を背景に、今年から「コミュニティZEHによるレジリエンス強化事業」に基づき、停電時でも自立的に電力の供給が可能なZEHを活用した地域防災拠点の整備を促進し、自然災害などに伴う長期停電リスクを回避可能な住宅モデルを推進している。
地域コミュニティで太陽光発電システム(PV)や蓄電システムを搭載したZEH+やZEH+Rを満たす住宅の余剰電力を、停電時に広く地域住民に提供し、地域住民はその電力で電気機器の充電などができる。ZEH+やZEH+Rを多数建築する同社はこの考えに共感し、コミュニティZEHの考えを取り入れた分譲地を広く展開する。なお、今年度、同事業に採択された15件のうち、同社の手掛ける分譲地が11件を占めている。
一方、近年多発している自然災害への備えとして、各家庭での対策だけではなく地域住民同士で支えあう「共助」が改めて注目されている。地震や災害が発生した際にも住民同士でスムーズな対応が行えるよう、「コミュニティZEHによるレジリエンス強化」では「共助」の考え方を取り入れている。日頃から停電時に利用可能な電気機器や時間帯などを地域住民と情報共有することで、停電時の円滑な電力提供はもちろんのこと、住民同士のコミュニケーションを促し地域コミュニティの形成もサポートする。
同社は今年度、国のコミュニティZEHの推進を受けて、7つの販売会社、11カ所の分譲地で「コミュニティZEHによるレジリエンス強化」を展開し、住民同士が助け合えるまちづくりを推進していく。