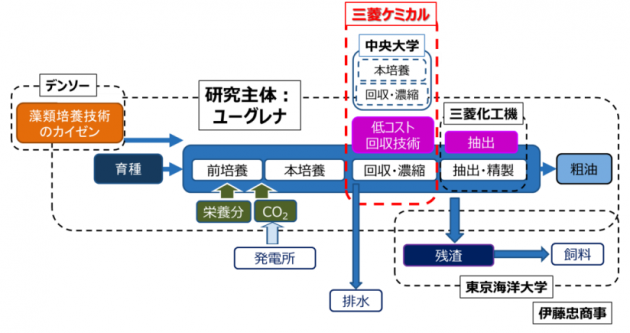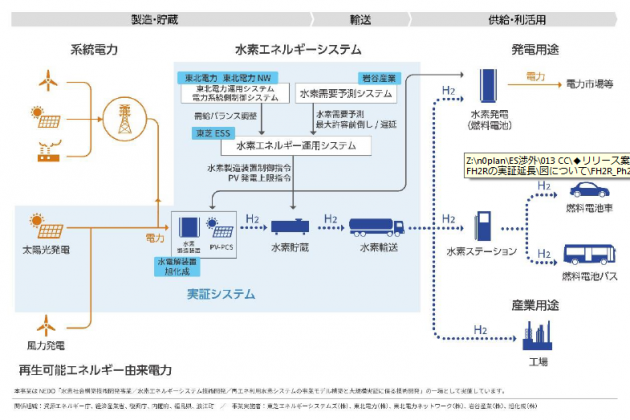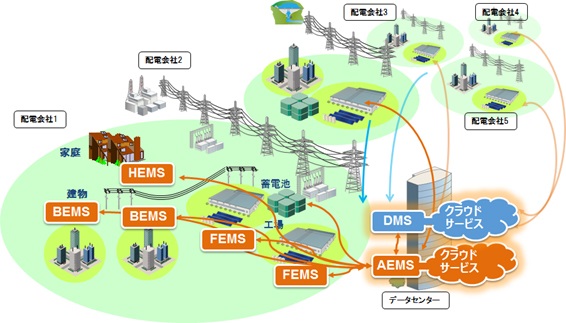新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)、東北大学、馬渕工業所、小浜温泉エネルギーはこのほど、温泉スケールと呼ばれる固形物が析出しやすい温泉水でも安定した熱交換が可能な熱交換器を開発し、1カ月間の温泉熱回収の実証試験に成功した。
今回開発した熱交換器は、熱交換器に付着した温泉スケールを自動的に取り除くことで、熱交換の効率を維持することが可能。これにより温泉水の熱交換器のメンテナンスコストの低減が見込める。また、温泉水以外にも、汚泥を含む工場温排水や藻類・貝類を含む海水・河川水など、様々な分野の熱交換に応用でき、未利用熱や再生可能エネルギーの利用促進が期待される。
一般的に温泉水はカルシウムや硫黄などの溶解成分を含み、熱交換器の伝熱面上に温泉スケールが析出し、熱交換を阻害することがある。そのため、頻繁な清掃が必要で、メンテナンスコストが高いことが課題だった。
こうした中、NEDOなど4者は「NEDO先導研究プログラム/エネルギー・環境新技術先導研究プログラム」に基づき、伝熱面を回転させ、そこに羽根を押し当てることで伝熱面に析出した温泉スケールを剥ぎ取れるようにした熱交換器を開発。これにより、表面を常時温泉スケールが付着していない状態に保つことを可能にし、熱交換の効率を維持することができる。また、小浜温泉(長崎県雲仙市)で1カ月間の熱交換実験を行った結果、伝熱面からの温泉スケールの除去と熱交換効率の低下抑制に成功した。
今後、スケールアップした熱交換器を開発し、長期間(3カ月を予定)の現地実証試験を行うことで、さらなる耐久性向上のための検証を行うほか、熱交換器の高性能化のための研究開発を行う。