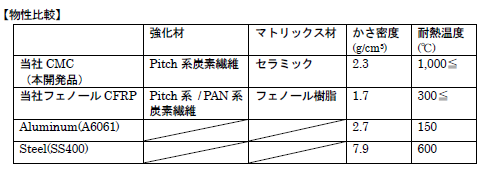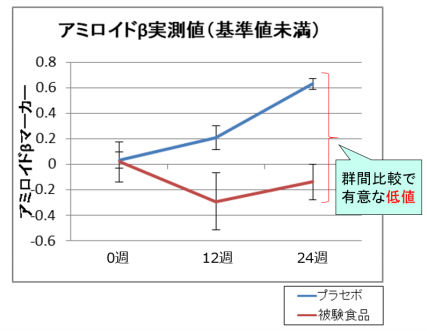出光興産は15日、同社と日本郵船グループが出資する郵船出光グリーンソリューションズが、石炭ボイラーにおけるバイオマス燃料の最適な混焼率を算出するシステム「BAIOMIX(バイオミックス)」を開発し、8月に販売開始すると発表した。なお、郵船出光グリーンソリューソンズが販売するボイラー制御最適化システム「ULTY-V plus」へ同システムを搭載することで、石炭ボイラーでのバイオマス混焼を最適に自動制御することが可能となる。
昨今、低炭素社会の実現を目指し、バイオマス燃料を石炭の代替とする動きが加速している。しかし、バイオマス燃料は石炭に比べ粉砕性や発熱量が劣るため、大型の微粉炭ボイラーでは使用量が制限されているのが実情。出光興産は、石炭火力発電所でのバイオマス混焼を拡大するため、粉砕性や発熱量などに優れ、石炭とほぼ同様に取り扱うことが可能な半炭化した木質ペレット「ブラックペレット」の開発を行っており、既存の石炭火力発電設備を利用したCO2の低減に取り組んでいる。
こうした中、今回開発した同システムは、「ブラックペレット」をはじめとしたバイオマス混焼による、機器や発電効率への影響・経済的負担を算定し、過去の混焼率データからAIが最適な混焼率を算出する。なお、石炭とバイオマス燃料を既存設備で混合してから燃焼する方式に加え、バイオマス燃料を専用ラインから投入し石炭と炉内混焼する方式など、さまざまな燃焼方式にも利用できる。
出光興産はエネルギーの安定供給とともに、地球環境をはじめとする社会課題の解決に貢献するため、2030年ビジョンとして「責任ある変革者」を掲げる。両社は、これからも顧客の声に耳を傾け、低炭素社会の実現に向けた製品づくりに努めていく。