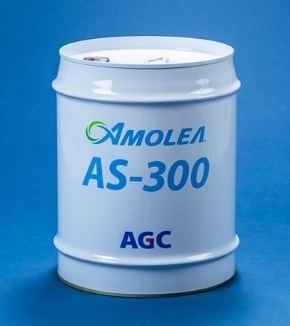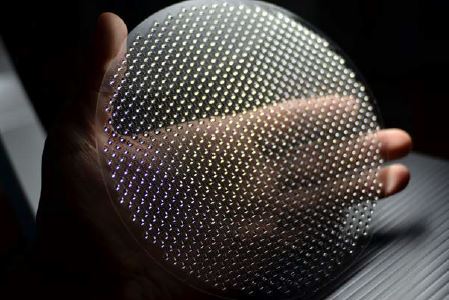JXTGエネルギーはこのほど、電気自動車(EV)やハイブリッド車(HV)の各駆動システムの特性に合わせた専用フルード「ENEOS EV FLUID」を開発したと発表した。EVやHVは今後さらに普及が見込まれている。それらのシステムには高い絶縁性能や冷却性能、ギヤ保護性能などを兼ね備えた専用フルードが求められる。
同社は、自動車潤滑油をはじめとした幅広い種類のオイル開発に長年にわたり携わっている。これらの開発を通じて蓄積された知見を活用することで、オイルに対する新たな必要性能を高いレベルで満足させる独自の潤滑油技術を確立した。様々な使用環境下でベストなパフォーマンスを発揮することができるよう、それぞれ特長を持った同シリーズを全6種類のラインアップで提供する。
まず、日本国内と中国を中心に、EVメーカーやHVメーカー、その関連部品メーカー向けに商品提案することを予定。その後、各国・地域の需要やニーズに応じて対象を全世界へ拡げることを目指す。また、将来的には一般消費者向け商品としての展開も検討していく。
同社グループは長期ビジョンの中で、「グローバルトレンドに適応する商品開発の推進」を潤滑油事業の将来像として掲げている。日々進歩を続けるEVやHVの駆動システムに対応する独自の潤滑油技術を通じて、今後も同社は、革新的な技術と有用な商品・サービスを開発・提供し続けることで、顧客の満足と信頼獲得に努めていく。