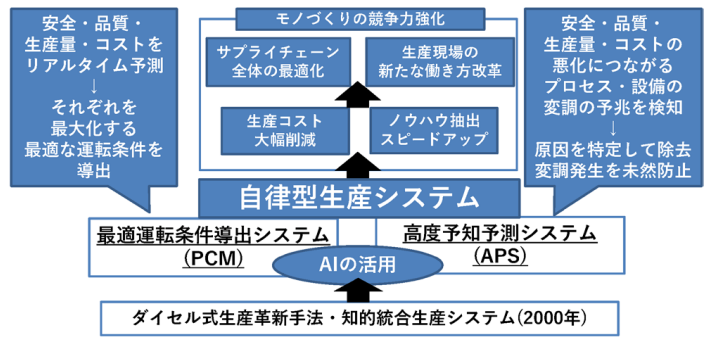東京大学、富山高等専門学校、筑波大学、北里大学と産業技術総合研究所(産総研)はこのほど、特異な構造相転移挙動により高溶解性・高移動度・環境ストレス耐性をもち、高製造プロセス適性かつ高性能な有機半導体を開発したと発表した。その成果は、アメリカ化学会(ACS)学会誌のオンライン速報版で公開された。
有機半導体は低分子間力の固体であり軽量・柔軟で、印刷で製造できるため低生産コスト・低環境負荷である。性能も市販アモルファスシリコンより1桁以上高い10㎠/Vs級の移動度をもち、次世代のプリンテッド・フレキシブルエレクトロニクス材料として期待される。しかし、高性能有機半導体分子の多くは有機溶媒への溶解性が乏しく、製造プロセスが限られることが課題であった。
同研究グループが開発したデシル置換セレン架橋V字型分子C10-DNS-VWは、製造プロセス適性と高性能を両立している。SPring-8による構造解析で、高溶解性だが低電荷輸送性の1次元集合体構造と、高電荷輸送性だが低溶解性の2次元集合体構造の2種類の集合体構造を形成し、加熱処理により1次元から2次元に、良溶媒存在下では2次元から1次元へ相転移することが分かった。
また分子動力学計算では基板表面では2次元集合体構造は1次元構造よりも安定であり、蒸着法や塗布結晶化法などの製造プロセスによらず、薄膜作製時に2次元構造が再現性よく得られた。一般的な芳香族溶媒に対して1重量%以上溶解するため、様々な印刷プロセスに適用できる。塗布プロセスで得られた単結晶薄膜を用いたトランジスタは、世界最高レベルの11㎠/Vsの移動度、良好な電荷注入特性、高環境ストレス耐性を示した。
今回開発のC10-DNS-VWからなる有機半導体は、蒸着法や印刷法などの各種製造プロセスへの適合性が高い。電子タグやマルチセンサーなど各種ハイエンドデバイス開発を加速し、次世代プリンテッド・フレキシブルエレクトロニクス分野の起爆材料となることが期待される。