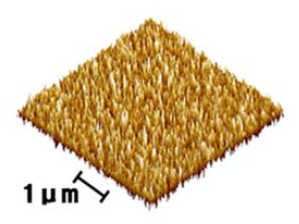ダウはこのほど、プラスチック廃棄物の抑制、GHG排出削減、化石燃料由来のバージン・プラスチックと同等の性能をもつリサイクルプラスチック製品を顧客へ提供する取り組みが進展しており、2022年から、完全循環型ポリマーを顧客へ初期供給することができると発表した。
同社は、気候変動およびプラ廃棄物に対応するために、サステナビリティ目標の達成に向けて重要な段階を進めている。2030年までに、直接またはパートナシップを通じて100万tのプラを回収、再利用、リサイクルし、2035年までに包装用に販売される製品の100%を再利用またはリサイクルを可能にする目標を設定している。
具体的な取り組みとして、オランダでは、フエニックス社との間で循環型プラ生産の拡大に向けた初期契約を拡大し、第2工場をヴェールトに建設する。同工場では2万tの廃プラが熱分解原料油に加工処理され、ダウの生産拠点(テルネーゼン)において循環型プラの生産に使用される。また、グンバー社との間では同原料油を精製する最終契約を締結。今年からクラッカーに対応した原料をダウに供給する。
ダウも、同原料油の精製能力を拡大するために、テルネーゼン拠点において市場開発規模での精製装置の設計、エンジニアリング、建設を進めている。また、米国では、ニューホープエナジー社(テキサス州タイラー)との間で、リサイクルプラ由来の熱分解原料油の供給について複数年契約を締結し、ダウはそれを原料に循環型プラを生産する計画。さらに、循環型プラ製品の認定取得にも力を注ぐ。欧州各国および米国の主要拠点において、国際持続可能性カーボン認証(ISCC)の取得を進めている。
一方、ダウは高度なプラスチックリサイクルソリューションの世界的パイオニアであるミュラ社と提携した。ミュラ社の新しい高度リサイクルプロセスである「HydroPRS」(熱水プラスチックリサイクルソリューション)は、これまでリサイクルできず焼却や埋め立て処分されていた包装軟質プラをはじめ、あらゆる形態のプラスチックがリサイクルできる。
現在、ミュラ社は同プロセスを用いた世界初の工場を、英国のティーズサイドで建設中。2023年には年間2万tの最初の生産ラインが稼働を開始し、ダウはリサイクル原料として供給を受ける予定だ。